防災対策として注目されるローリングストックですが、「管理が大変で続かない」と感じ、やめた方も多いのではないでしょうか。賞味期限を管理表で追いかける手間や、どんな食品を備蓄すれば良いかという悩みは尽きません。
この記事では、ローリングストック法の欠点は何ですか?という根本的な疑問に答えつつ、失敗しないための実例を具体的に解説します。また、備蓄をしていない人の割合や、実際に防災グッズで助かった人の割合、そして防災グッズで本当にいらないものランキングといった客観的なデータも参考にします。さらに、非常食長持ちランキングに入るようなおすすめ商品や、おすすめスーパー、おすすめ無印アイテムまで、具体的で実践的な情報をお届けします。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- ローリングストックが続かない理由と具体的な欠点
- データで見る防災グッズの必要性と備蓄の現状
- やめた人向けの無理なく続く代替案と管理方法
- スーパーや無印で揃うおすすめの長期保存食品
ローリングストックをやめた理由と現状

- ローリングストックが続かない原因とは
- ローリングストック法の欠点は何ですか?
- 備蓄管理表の作成が負担になる実例
- 備蓄をしていない人の割合と防災意識
- 防災グッズで助かった人の割合は低い?
ローリングストックが続かない原因とは
ローリングストックが続かない背景には、その仕組みが日常生活に馴染みにくいという理由が存在します。
主に考えられるのは、「管理の複雑さ」です。この方法は、日常的に食品を消費し、消費した分を買い足すことで常に一定量の備蓄を保つという考え方に基づきます。しかし、これを実践するには「在庫の把握」「賞味期限の確認」「補充リストの作成」「計画的な買い物」といった複数の工程を継続的に行う必要があります。多忙な毎日の中で、これらの作業を常に意識し続けることは、想像以上に大きな負担となり得ます。
加えて、ライフスタイルとの不一致も一因です。例えば、普段あまりレトルト食品や缶詰を食べない家庭が、備蓄のためにこれらを無理に食生活へ取り入れると、消費が進まずに賞味期限切れを起こしやすくなります。逆に、無印良品のカレーのように好みの食品を備蓄した場合、非常時を待たずに普段のおいしい食事としてすぐに消費してしまい、いざという時のための在庫がなくなってしまうという実例も少なくありません。
これらのことから、ローリングストックは便利な方法である一方で、各家庭の生活習慣や管理能力に合わない場合、継続が困難になる傾向があると言えます。
ローリングストック法の欠点は何ですか?
ローリングストック法には、災害時に食べ慣れた味で安心できるなどのメリットがある一方、実践する上でいくつかの欠点が指摘されています。
最大の欠点は、賞味期限の管理に手間がかかる点です。備蓄する食品の種類が増えれば増えるほど、それぞれの期限を把握し、古いものから計画的に消費していく作業は煩雑になります。特に家族の人数が多く、必要な備蓄量が多い家庭では、その負担はさらに大きくなるでしょう。管理を怠ると、気づいた時には賞味期限が切れており、食品ロスにつながる可能性も高まります。
次に、保管スペースの確保も課題となります。普段の買い物に加えて備蓄分をストックするため、キッチンや収納スペースが圧迫されがちです。限られた住空間の中で、非常食の置き場所を確保し続けることにストレスを感じるケースも考えられます。
さらに、食生活との相性も無視できません。前述の通り、普段レトルトや缶詰を多用しない家庭にとっては、備蓄品を日常的に消費すること自体が苦痛になる可能性があります。災害時のためとはいえ、好きではないものを定期的に食べなければならない状況は、精神的な負担につながりかねません。
このように、ローリングストック法は、その維持・管理に継続的な労力と工夫が求められるため、誰にとっても最適な方法とは限らないのです。
備蓄管理表の作成が負担になる実例

ローリングストックを実践しようと試みる多くの方が直面するのが、備蓄管理表の作成とその後の運用が大きな負担となるという現実です。
最初は意欲的に、品名、購入日、賞味期限、数量などをExcelやスプレッドシート、あるいはノートに書き出して管理を始めます。しかし、日々の生活の中でこの管理表を常に最新の状態に保つ作業は、想像以上に手間がかかります。例えば、食品を一つ消費するたびに表を更新し、買い物をしたら新たに行を追加するという作業を、毎回忘れずに行うのは容易ではありません。
実例として、共働きで忙しい家庭では、週末にまとめて買い物をすることが多く、消費と補充のタイミングがずれやすくなります。その結果、管理表への記入が追いつかなくなり、次第に更新が億劫になってしまうのです。一度更新が滞ると、実際の在庫と表の内容に差異が生まれ、管理表そのものが機能しなくなります。
また、スマートフォンのアプリを利用するケースもありますが、入力の手間自体は変わらないため、結局は使われなくなってしまうことも少なくありません。このように、管理を完璧に行おうとするあまり、その手段であるはずの管理表の維持が目的化してしまい、結果として「面倒だから」とローリングストック自体をやめてしまう原因の一つになっています。

備蓄をしていない人の割合と防災意識
近年の調査によると、災害や非常事態に備えて食品などを備蓄している人の割合は約6割にのぼります。これは、多くの方が防災への意識を持っていることを示しています。
特に、新型コロナウイルスの流行を経験したことで、備蓄の重要性が再認識されたと考えられます。実際に、「備蓄をしたことがない」と回答した人の割合は、2019年10月の時点では37%でしたが、その後24%へと大きく減少しています。このデータから、社会全体で防災意識が高まっている傾向がうかがえます。
一方で、見方を変えれば、まだ約4割の人は十分な備蓄ができていないという現状も浮き彫りになります。備蓄を行っている世帯の内訳を見ると、ひとり暮らしの世帯よりも、夫婦のみや子どもがいる世帯の方が備蓄率が高い傾向があります。これは、守るべき家族がいることで、より一層防災への意識が強まるためと推測されます。
このように、防災意識は高まりつつあるものの、全ての人が十分な備えを完了しているわけではありません。ローリングストックのような継続が難しい方法だけでなく、より手軽で実践しやすい備蓄方法の情報提供が、備蓄をしていない層へのアプローチとして大切になると考えられます。
防災グッズで助かった人の割合は低い?
防災グッズを準備していても、実際の災害時に本当に役立ったと感じる人の割合は、残念ながら決して高くないという調査結果があります。
ある自然災害の被災経験者を対象とした調査では、防災グッズを「用意していて役に立った」と回答した人は、全体のわずか9%に留まりました。この数値は、多くの人が備えの重要性を認識しながらも、その内容が実際の被災状況と合致していなかった可能性を示唆しています。
対照的に、「用意していなかった」または「用意していたが不十分だった」と回答した人は合計で91%に達しており、準備不足が大きな課題であることが明確です。多くの被災者が、後になってから「もっとしっかり備えておけばよかった」と感じており、災害を経験して初めて本当に必要なものが何であったかを認識するケースが少なくありません。
このデータは、単に防災グッズを揃えるだけでなく、「何を」「どのように」備えるかがいかに大切かを示しています。防災グッズによって助かった人の割合が低いという現実は、私たちの備えがまだ改善の余地があることを教えてくれます。
ローリングストックをやめた後の備蓄術

- 防災グッズで本当にいらないものランキング
- 非常食長持ちランキングとおすすめ食品
- おすすめ商品はスーパーで手軽に購入
- 無印良品のおすすめ備蓄アイテム紹介
- ローリングストックをやめた人向け備蓄法
防災グッズで本当にいらないものランキング
災害への備えとして様々な防災グッズが推奨されていますが、中には被災経験者の声から「実際には使わなかった」「他のもので代用できた」とされるものも少なくありません。ここでは、防災グッズで本当にいらないものとして挙げられがちなアイテムを、その理由とともに紹介します。
| 不要とされがちな防災グッズ | 主な理由 |
| コンパス・ロープ | 避難場所が分かっている場合、使い道が限定的。素人が使いこなすのが難しい。 |
| カップ麺・大量の食器 | 貴重な水を大量に消費する(調理・洗浄)。ゴミがかさばる。 |
| 手回しラジオ・発電機 | 手間がかかる。スマートフォンやモバイルバッテリーで情報収集する方が効率的。 |
| 携帯浄水器 | 普段から備蓄しているペットボトルの飲料水の方が安全で確実。 |
| テント・毛布 | 避難所には備え付けられている場合が多く、荷物がかさばる原因になる。 |
| ろうそく | 火災のリスクがあり危険。安全なLEDライトやランタンの方が推奨される。 |
これらのアイテムが不要とされる背景には、避難生活の現実があります。例えば、カップ麺は手軽に感じますが、断水時には調理に使う水も、スープを飲むための水も非常に貴重です。
もちろん、アウトドアでの避難など特殊な状況下では役立つ可能性も否定できません。しかし、多くの人が経験する在宅避難や避難所生活においては、電力の確保(モバイルバッテリーなど)、衛生用品(携帯トイレ、ウェットティッシュ)、そして何よりも水と食料の方がはるかに優先度が高いと言えます。このランキングを参考に、ご自身の備蓄内容を見直してみてはいかがでしょうか。
非常食長持ちランキングとおすすめ食品
ローリングストックをやめた方や、管理の手間を減らしたい方にとって、長期保存が可能な非常食は非常に有効な選択肢となります。ここでは、特に賞味期限が長く、備蓄に適した食品のカテゴリーとおすすめを紹介します。
5年以上の長期保存が可能な食品
近年、技術の進歩により、5年以上の長期保存が可能な美味しい非常食が増えています。これらは一度購入すれば、次の買い替えまで数年間は管理の手間がほとんどかかりません。
- アルファ米: お湯や水を注ぐだけでご飯が食べられる非常食の定番です。白米だけでなく、五目ごはんやピラフなど味の種類も豊富で、飽きずに食べられます。
- 缶詰パン: 「パンの缶詰」は、缶を開けるだけで柔らかいパンが食べられるため、子どもからお年寄りまで人気があります。
- レトルトの長期保存食: 災害用に開発されたレトルト食品の中には、7年や10年、中には25年保存できるものもあります。味や食感も改良されており、非常時でも満足感のある食事が可能です。
日常備蓄にもなるおすすめ食品
長期保存専用の食品だけでなく、普段の食品の中にも比較的日持ちし、備蓄に向いているものがあります。
- フリーズドライ食品: 味噌汁やスープ、雑炊などが代表的です。軽量でかさばらず、お湯を注ぐだけで本格的な味が楽しめます。野菜が不足しがちな避難生活において、具だくさんのフリーズドライ味噌汁は栄養補給にも役立ちます。
- 乾麺: パスタやそうめん、そばなどは賞味期限が長く、主食として重宝します。カセットコンロと水があれば調理可能です。
これらの食品を組み合わせることで、管理の手間を最小限に抑えつつ、栄養バランスの取れた災害備蓄を構築することが可能になります。
おすすめ商品はスーパーで手軽に購入

災害用の特別な非常食を揃えようとすると、専門店やオンラインストアを探す必要があり、手間やコストがかかると感じてしまうかもしれません。しかし、実は普段利用しているスーパーマーケットでも、備蓄に適したおすすめ商品を数多く手軽に購入することができます。
最も活用しやすいのが、スーパー各社が展開しているプライベートブランド(PB)の商品です。PB商品は、ナショナルブランドの商品に比べて価格が手頃である場合が多く、計画的に流通されているため賞味期限が長めのロットが見つかりやすいというメリットがあります。缶詰、レトルトカレー、パックご飯、パスタといった基本的な備蓄品は、PB商品で十分に揃えることが可能です。
また、スーパーでは以下のような商品も日常の買い物ついでに購入できます。
- 缶詰: さばの味噌煮缶やツナ缶などは、調理不要でタンパク質を摂取できる優れた備蓄品です。フルーツの缶詰はビタミン補給や、甘いものが欲しくなった時に役立ちます。
- レトルト食品: 温めるだけで食べられるカレーや丼ものの素は、普段の食事で消費しながら多めにストックしておく「ゆるいローリングストック」にも向いています。
- 飲料水: 2リットルのペットボトルを箱単位で購入しておけば、飲用から調理用まで幅広く活用できます。
このように、防災備蓄は特別なことと捉えず、いつもの買い物の延長線上で少し意識するだけでも始めることができます。まずは、次回の買い物で缶詰や水のストックを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
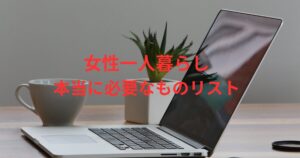
無印良品のおすすめ備蓄アイテム紹介
シンプルで質の良い商品が揃う無印良品は、防災備蓄に役立つアイテムの宝庫でもあります。特に、食品は「いつもの味」を備えられるという点で、災害時の食のストレスを軽減するのに役立ちます。
人気のレトルト食品
無印良品の代名詞とも言えるのが、豊富な種類のレトルトカレーや「ごはんにかける」シリーズです。
- 素材を生かしたカレー バターチキン: 定番かつ人気のカレーで、子どもから大人まで食べやすい味わいです。
- ごはんにかけるシリーズ: ルーロー飯やガパオなど、世界各国の料理を手軽に楽しめます。白米さえあれば、食事が単調になるのを防げます。
これらのレトルト食品は、普段の食事としても美味しいため、自然な形で消費と補充がしやすいのがメリットです。ただし、前述の通り、美味しさゆえにすぐに食べてしまい、いざという時の在庫が不足する可能性もあるため、計画的な管理が求められます。
ローリングストックセット
無印良品では、ネットストアや一部店舗限定で「ローリングストック レトルトセット」を販売していることがあります。これは、人気のカレーやハンバーグ、丼ものの素などを詰め合わせたセットで、何を備えたら良いか分からないという方の最初のステップとしておすすめです。
食品以外にも、カセットこんろやLEDライト、長期保存できる備蓄おやつ(チョコようかんなど)も取り扱っており、無印良品だけで基本的な備蓄をトータルで揃えることも可能です。
ローリングストックをやめた人向け備蓄法

- ローリングストックが続かないのは管理の手間が主な原因
- 賞味期限の確認や計画的な買い足しが負担になりやすい
- 無理なく続ける代替案として長期保存食の活用が有効
- 5年以上の賞味期限を持つ非常食も多数販売されている
- 防災費として日々の食費と予算を分けると管理が楽になる
- 無理に食品を循環させず年に一度の確認で済む方法を選ぶ
- 日本の備蓄率は約6割で防災意識は向上傾向にある
- しかし被災経験者の9割以上が備えは不十分と感じている
- カップ麺など水を多く使う食品は非常時に不向きな場合がある
- 本当に役立つのはモバイルバッテリーや携帯トイレなどの生活用品
- 普段利用するスーパーのプライベートブランド商品も備蓄に活用できる
- 無印良品などの美味しいレトルトは試食を兼ねて備蓄に加える
- 食べ慣れた味の食品は災害時の大きなストレスを軽減する
- 家族構成やアレルギーの有無に合わせて必要なものを備える
- 自分や家族に合った無理のない方法を見つけることが継続の鍵となる


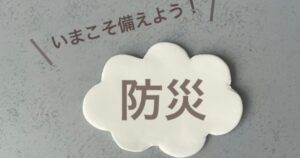
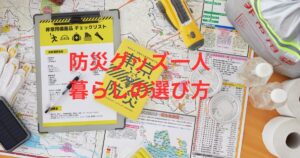
コメント